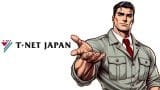発注者支援業務って、施工管理からの転職先として人気が出てきてるよな。土日祝休みで残業も少ないって聞けば、「次はそっちかも」って考えるやつも多いと思う。
でも実際に働いてみると、現場とはまったく違う空気や、意外と人間関係で悩むこともあって、「思ってたのと違うな…」ってなるケースもあるんだ。
今回は、ティーネットジャパンで発注者支援業務を経験した dobokuyaさん に、リアルな実情を語ってもらった。
待遇、キャリア、働き方のギャップ、後悔ポイントまで、本音で話してくれてるから、気になる人はじっくり読んでみてくれ。
はじめに:発注者支援業務の「理想」と「現実」

発注者支援業務って、施工管理から転職される方も多いと聞きますが、実際に働いてみて「想像通りだったこと」と「ギャップを感じたこと」があれば教えていただけますか?

まず良かったと感じたのは、休日がしっかり取れて、残業もそこまで多くないという勤務環境です。これは転職前に期待していた通りでした。
ただ、意外だったのは、人との関わりが想像以上に多かったことですね。地味な内勤仕事かと思っていたら、発注者・受注者・地域住民など、いろんな立場の人と接する場面が意外と多くて、正直そこはギャップを感じました。
発注者支援業務の「理想」:休みやすさと安定した労働時間
発注者支援業務の大きな魅力は、働き方の安定性と生活リズムの整えやすさにあります。
技術者は基本的に発注機関と同じ庁舎内で勤務するため、土日祝日は原則休み。残業も、特殊な現場を除けば月20~30時間前後と比較的少なめです。
施工管理職の現場では、週末に現場が止まっていても、所長や主任技術者だけは出社して、たまった書類に追われる…というのが珍しくありません。
そういった実情と比べると、発注者支援業務では業務量が日中に整理されており、カレンダー通りの生活が可能になるケースが多くなります。
現実①:想像以上に多い「人との関わり」
一方で、実際に現場に出てみると「思っていたのと違う」と感じることもあります。
例えば、事前には「発注者の指示に従って、パソコンで報告書をまとめるような内勤中心の仕事」だとイメージしていた方もいるかもしれません。
ところが実際は、受注者や地元住民、関係機関との調整など、人との折衝業務が想像以上に多いのが実態です。
こうした対外的なやり取りには、ある程度のコミュニケーション能力や対応力が求められます。「一人で黙々とこなす仕事がいい」と思っていた方にとっては、最初にぶつかるギャップかもしれません。
現実②:職場異動と人間関係の再構築
また、発注者の職員は2〜3年ごとに異動することが多く、それに連動して、発注者支援業務の契約自体も切り替わるケースがあります。
そのため、技術者側も現場との契約終了に合わせて別の現場へ異動になる可能性が高いのです。
一つの職場で信頼関係を築けたとしても、数年後にはまったく異なる職場でゼロから関係構築を始めなければならないという状況が繰り返されます。
人間関係の構築にストレスを感じない方にとっては大きな問題にならないかもしれませんが、人付き合いが得意でない方には精神的な負荷が大きくなる場面もあるでしょう。
理想と現実のギャップを知ることが第一歩
発注者支援業務は、「ワークライフバランスを改善したい」と考えている施工管理経験者にとって、有力な選択肢のひとつです。
ただしその反面、自分で主導権を持って進めたい人や、人間関係の再構築が苦手な人にとっては、環境の変化や業務の特性がストレスになることもあります。
理想と現実の両面を理解したうえで、「この働き方は自分に合っているのか?」を冷静に判断することが、転職成功の鍵になります。
ティーネットジャパンの弱みとは?

発注者支援業務って、働きやすそうなイメージがありますが、やっぱり企業ごとに課題もありますよね。ティーネットジャパンで働いてみて、「ここは弱いな」と感じたポイントがあれば教えていただけますか?

ええ、もちろん良い面も多いですが、実際に働いていると「もう少し改善できるのでは」と感じるところもあります。
具体的には、給与の構造やキャリアパスの選択肢の少なさ、そして業務内容の変化による違和感ですね。
待遇の現実:給与水準は「施工管理より上」とは限らない
発注者支援業務に転職する際、多くの方が気にするのが「給与は上がるのか?」という点でしょう。
結論から言うと、どの企業にいたか、どのポジションにいたかによって大きく変わります。
私の場合、前職より給与は上がりました。ティーネットジャパンでは、単身赴任手当、住宅補助、帰省費用の補助といった制度が整っており、技術士やコンクリート診断士などの資格手当もつきます。
ただし注意すべきなのは、残業代や休日出勤手当が期待できないということです。
施工管理時代は「平日は遅くまで残業、土日は現場対応や書類対応」といった働き方で、結果的に収入が底上げされていた人も多いと思います。
そうした人にとっては、たとえ基本給が同じでも実質的な手取りが下がる可能性がある、という点は理解しておいた方がいいです。
業務内容のギャップ:「現場を離れること」の違和感
発注者支援業務では、実際にモノを作るというよりも、発注者のサポートとして工程管理や品質チェック、文書整理などに徹する立場になります。
そのため、施工管理時代のように「自分で現場を動かす」感覚は薄れます。
現場でバリバリ動いてきた人にとっては、「あれ、自分って今何やってるんだろう?」と感じる瞬間もあるかもしれません。
特に、構造物が完成したときの達成感や、一体感のある現場の空気を大事にしていた人には、業務の地味さや間接的な立場に違和感を覚えることもあるでしょう。
キャリアパスの課題:管理職の道は狭き門
ティーネットジャパンでは、現場の技術者が目指せるキャリアパスは大きく2つ。
担当技術者として働き続けるか、管理技術者(または業務リーダー)に昇格するかです。
問題は、この「管理技術者」への昇格がかなりハードルが高いということ。
推薦、試験、上司の評価といった複数のステップを経る必要があり、かつ高い技術力、リーダーシップ、発注者との信頼関係が求められます。
実際、現場で長く働いている方でも、なかなか昇格のチャンスが巡ってこないという声もあります。
営業や管理部門であれば比較的年功序列も機能していますが、技術職に関しては実力・成果・資格ありきの昇進スタイルが徹底されています。
そのため、「将来的には管理職に…」と考えていた人にとっては、選択肢の少なさや昇格までの道のりの遠さに戸惑う場面があるかもしれません。
「条件だけでは見えない」ティーネットの課題を見極める
ティーネットジャパンは制度面や働きやすさの面では一定の評価がある一方で、
- 収入の仕組み(特に残業代の影響)
- 業務内容の変化に伴うやりがいの薄れ
- キャリアの一本道化
といった、転職前には見えづらい弱点も存在します。
もし「転職して年収が上がる」と期待しているなら、「基本給だけで判断しない」「残業代を含んだ前職の給与と比較する」という視点が不可欠です。
また、「キャリアを長く積んでいけるか」という観点でも、昇格条件や配属ルールの仕組みをあらかじめ確認しておくことが大切です。
発注者支援業務の働き方に関する負の側面

発注者支援業務って、施工管理よりは働きやすいという話をよく聞きますが、実際にはストレスのかかる場面もあると思います。働き方に関して、特に気をつけるべき点があれば教えていただけますか?

たしかに、現場のような激務ではないですが、別の種類の難しさがありますね。
発注者と受注者の間に立つ調整役という立場上、自分の判断で動けないストレスや、発注者側との人間関係に悩まされることもあります。
判断できないつらさ:調整役という立場のもどかしさ
発注者支援業務は「発注者側の立場」と言われることが多いですが、実際には完全な内側の人間ではありません。
技術者はあくまで外部の業務委託という位置づけで、発注者と受注者の間に立つ調整役として動くことになります。
そのため、業務を進める中で「この内容は明らかにおかしい」と感じたとしても、自分の判断だけでは止めることができません。
たとえば、発注者からの指示が受注者にとって明らかに不利だったとしても、「それは間違っている」と正面から異を唱えるのは非常に難しい立場です。
納得できない内容でもそのまま受け入れざるを得ないという、精神的に苦しい場面があるのは事実です。
現実に起こる理不尽:職場により変わる人間関係のストレス
発注者支援業務の現場には、発注者職員との関係性が大きく影響します。
中にはフラットに接してくれる方もいますが、明らかに業務委託を見下すような態度をとる職員も存在します。
高圧的な態度や、感情的に怒鳴られる場面が続くと、技術者としてだけでなく人としての尊厳が傷つきます。
しかも業務委託という立場では、こうした問題に対して強く主張するのが難しく、会社も発注者との関係を悪化させたくないため、根本的な解決につながらないケースがほとんどです。
結果的に、泣き寝入りしたり、自分を責めてしまったりして、精神的に追い詰められる人もいます。
デスクワーク中心の仕事に対する違和感
もうひとつの特徴として、発注者支援業務はデスクワークが中心です。
施工管理時代は、毎日現場に出て職人とやりとりし、工程を調整し、トラブルをその場で判断して動かす、そんな仕事が当たり前だったと思います。
それが発注者支援業務では、基本的に事務所での内勤となり、書類のチェックや調整、報告書の作成などが主な仕事になります。
目に見える成果や構造物の完成をモチベーションにしてきた方には、間接的な業務内容にストレスを感じる可能性があります。
発注者支援業務の「働きやすさ」は一面的ではない
発注者支援業務は、たしかに施工管理と比べて労働時間や休日の面で恵まれていると言えます。
しかし、判断の自由度が低いことや、対人関係のストレス、仕事のやりがいに関する違和感といった、目には見えにくい負の側面もあることを理解しておく必要があります。
環境や立場が整っている分だけ、精神的なバランスをどう保つかが問われる仕事でもあります。
これらの点を踏まえて、自分に合った働き方かどうかをしっかり見極めることが大切です。
ティーネットジャパンの社内環境と組織の課題

発注者支援業務って、現場よりも働きやすい印象がありますけど、会社の中の制度や組織の雰囲気ってどうなんですか?評価のされ方や育成面についても気になります。

働きやすさはたしかに感じましたが、その一方で「評価の仕組みが見えにくい」「研修はあるけど受け身では意味がない」など、気になる部分も正直あります。
評価制度はあるが、現場次第の側面も
ティーネットジャパンでは、担当技術者に対して年に1回、管理技術者や営業所長からの評価があります。
評価項目は勤務態度、業務の実績、コンプライアンスの遵守、自己研鑽の姿勢など多岐にわたります。
ただし、現場ごとの発注者や上司との関係性、業務の内容によって評価が左右されやすい側面もあります。
特に発注者からの印象が良ければ「引き続きこの人に担当してもらいたい」と評価が上がる傾向があるため、技術力そのものよりも対人スキルが重視される場面も少なくありません。
自己研鑽が重視される文化
ティーネットジャパンでは、スキルアップを会社任せにするのではなく、個人の学ぶ姿勢が評価される傾向があります。
研修制度は整っており、着任時研修や年2回の全体研修、専門分野別の技術研修などが用意されています。
ただ、それらを受けているだけでは評価に繋がるとは限りません。
積極的に資格を取得したり、外部講習を受けたりするなど、自主的に行動しているかが重視されるのが実情です。
実際、技術士やRCCMなど難易度の高い資格を取得している人は、社内評価が高くなる傾向があります。
年功序列の傾向は限定的
営業職など管理部門では、年次に応じた昇進が一定程度見られる一方、技術職に関しては完全に実力主義に近い形が取られています。
たとえば、若手であっても発注者との信頼を築き、業務を安定して遂行できれば評価されますし、逆に年次が上でもトラブルが多いと評価は上がりにくいというのが実態です。
そのため、評価される人とそうでない人の差が大きく、納得感を得にくいという声も現場では聞かれます。
発注者との関係性が評価にも影響
技術者の評価において最も大きいのは、実は発注者からの印象かもしれません。
たとえ高い技術を持っていたとしても、発注者と折り合いが悪く、業務の進行に支障が出れば、それは会社にとっても問題となります。
逆に、「あの人にまたお願いしたい」と発注者側から声がかかるような技術者は、社内での信頼も厚くなります。
発注者支援業務では、技術力と同じくらい、人間関係の構築力が重要視されるという現実があります。
制度はあるが、使いこなすには主体性が必要
ティーネットジャパンは、制度上の整備は比較的進んでいます。
しかし、与えられた研修や評価制度をどう活用するかは、技術者個人の意識次第です。
言われた通りに仕事をこなすだけでなく、自分から学びに行く姿勢を持つ人ほど、チャンスを得やすい環境だと言えるでしょう。
その反面、受け身のままでは思ったような評価が得られず、「何年働いても立場が変わらない」と感じてしまうリスクもあります。
施工管理経験者が転職後に直面する「後悔ポイント」

発注者支援業務に転職したあと、「やっぱり施工管理のほうがよかったかも」と感じることってあるんでしょうか?現場に未練が残るケースもあるんですかね。

正直なところ、そう感じる人もいます。ただ、私は今の仕事に満足していますし、施工管理に戻りたいと思ったことはないですね。
でも「思っていたのと違った」と感じる場面は確かにあります。
現場を離れて感じる「やりがいの差」
施工管理の仕事は、構造物を自らの指揮で動かし、完成までを見届けるという大きなやりがいがあります。
一方で発注者支援業務は、あくまでも監督補助の立場です。工事全体に関わることはできても、自分が中心になって工事を動かすという感覚は薄れます。
「ものづくりがしたい」「自分の裁量で現場を進めたい」という思いが強い方にとっては、物足りなさを感じることもあるでしょう。
仕事の達成感が見えにくいと感じる瞬間
発注者支援業務では、完成物そのものではなく、書類の正確さや工事全体の適正な流れが求められます。
そのため、現場での直接的な達成感というより、陰から支える役割としての満足感が中心になります。
最初は「本当に自分が貢献できているのか」と不安になる人も少なくありません。
ただ、大規模な公共インフラが完成したとき、地域住民から感謝の声を聞いたり、発注者から信頼されるようになると、大きなやりがいを実感する瞬間があります。
合わないと感じる人の傾向とは?
発注者支援業務は、工事の実行ではなく、支援や監督、調整が主な仕事になります。
そのため、次のような志向を持つ方には向いていない可能性があります。
- 自分で構造物を完成させたい人
- 現場での裁量を重視する人
- 外に出て動くことが好きな人
- 発注者側の業務に興味が持てない人
逆に、内業が得意な人や、計画・調整・書類対応が好きな人、社会的意義のある仕事にやりがいを感じる人には向いている仕事です。
「後悔」よりも「視点の切り替え」が鍵になる
私自身は、発注者支援業務にやりがいを感じています。
特に、橋梁やトンネルといった大規模プロジェクトに関わり、それが地域のインフラとして長く使われていくという事実には誇りを持っています。
自分が主導する立場ではなくても、社会に役立つ仕事に関わっているという実感はあります。
もし「この仕事は自分に合わないかも」と感じた場合でも、すぐに辞めてしまうのではなく、自分に合った業務や担当領域を見つけることが先です。
発注者支援業務には、積算・資料作成・技術審査など、いくつかの種類があります。環境を変えることで、向いているポジションに出会える可能性もあります。
最終的に現場に戻る選択をするにしても、発注者側の視点を経験することは、施工管理の仕事にも必ずプラスになると思います。
まとめ:ティーネットジャパンで働く前に知っておくべきこと

発注者支援業務って、向いている人とそうでない人が分かれそうですね。最後に、ティーネットジャパンに転職する前に考えておくべきことがあれば教えてください。

そうですね。施工管理と比べて良い点も多いですが、違う仕事だと割り切って捉えることが大事です。働き方の変化や業務内容の違いを、事前にしっかり理解しておく必要があります。
施工管理と比べたときの働き方の違いを知る
発注者支援業務の担当技術者は、基本的に発注者と同じ執務室に常駐し、工事の進捗や品質、安全面を発注者の立場から確認・支援する業務を担います。
そのため、早朝出勤や夜間作業への対応が必要な施工管理に比べて、始業・終業時間は安定し、土日祝日も原則休みになります。
一方で、施工管理時代のように自分の裁量で現場を動かすような自由さや、手を動かして現場をつくりあげる実感は少なくなります。
その違いを正しく理解せずに転職すると、「イメージと違った」と後悔する可能性もあります。
仕事の進め方や役割の違いにも注意
施工管理ではチームで現場を動かすスタイルが一般的ですが、発注者支援業務は基本的に一人で業務を完結させることが求められます。
また、工事の方針や変更の判断は発注者が行うため、自分で決断して動くというよりは、確認や調整を通じてサポートする役割になります。
そのため、コミュニケーション力や調整力が問われる場面が多く、書類作成や手続きの正確さも重要です。
転勤の可能性があることも想定しておく
発注者支援業務は1〜2年単位での業務委託契約が多く、次の年度で契約が切れた場合は、近隣の別の発注機関や県外への転勤になることもあります。
施工管理時代と比べると、勤務エリアが安定しないケースもあり、家族がいる方は転勤への対応を事前に検討しておく必要があります。
自分に合う業務や職場を見つける柔軟さが必要
発注者支援業務とひとくちに言っても、監督補助だけではなく、積算や技術審査、資料作成など、さまざまな種類の業務があります。
発注者も国交省、地方自治体、NEXCOなど多岐にわたり、業務のやり方や職場環境も異なります。
万が一、最初の配属先で合わないと感じたとしても、すぐに辞めるのではなく、別の業務や現場で自分に合った働き方を模索してみるのも一つの手です。
発注者側の経験は、施工管理に戻っても活きる
たとえ将来的に施工管理に戻るとしても、発注者の視点や考え方を経験しておくことは、施工管理の仕事においても大きな財産になります。
契約の考え方や発注者の意図を汲み取るスキルは、元受側の仕事をするうえで非常に役立ちます。
転職後にギャップを感じることはあっても、無駄になる経験ではありません。
だからこそ、目先の条件だけで判断するのではなく、自分のキャリア全体の中で「どんな経験を積んでおくべきか」を冷静に考えることが大切です。