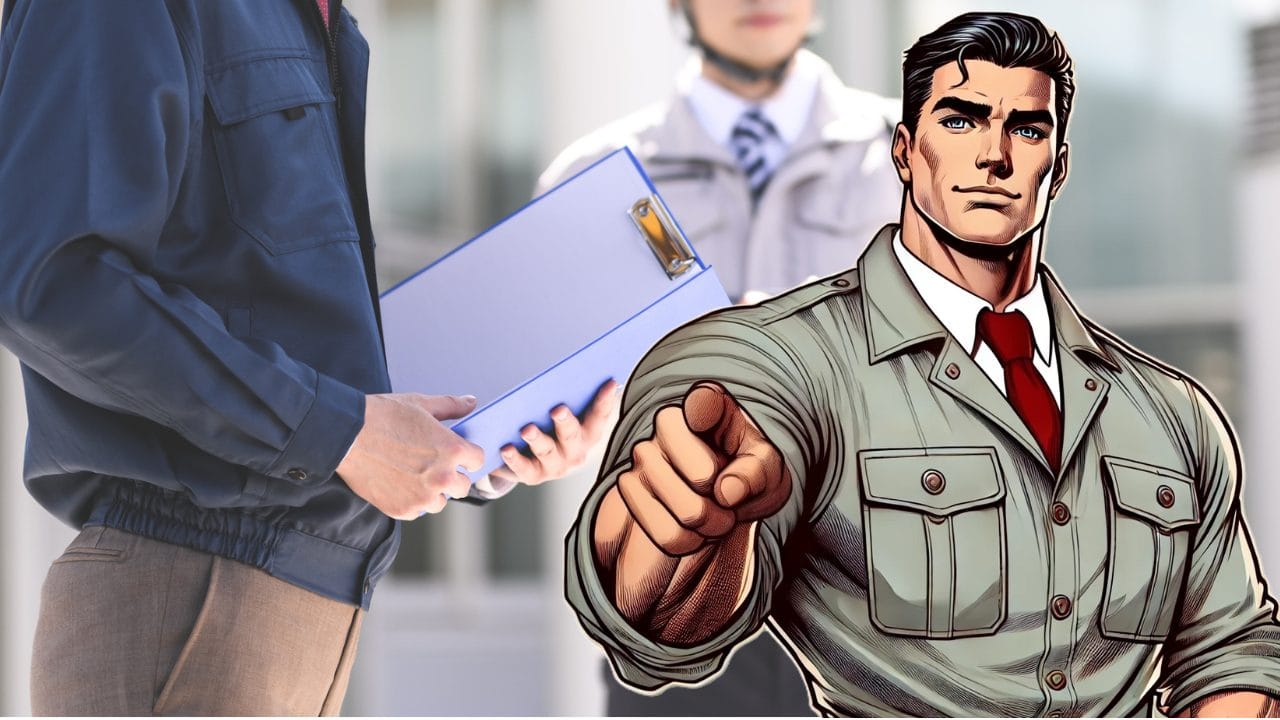「発注者支援業務って、施工管理よりも楽そう」「残業も少ないしホワイトっぽい」──そんな声、最近よく耳にするようになったな。でも実際のところ、ほんとにそうなんだろうか?
今回の記事では、ティーネットジャパンで実際に発注者支援業務に携わっていたdobokuyaさんに、現場で感じた働き方のリアルをじっくり聞かせてもらった。
結論から言うと、たしかにワークライフバランスの面では施工管理よりも恵まれてる。けど、その裏には「思っていたより人間関係が大変」「裁量が少なくてやりがいに悩む」といった“見えにくい課題”もあったんだ。
これから転職を考えてる技術者にとって、「自分に合った働き方」を見極めるためのヒントが詰まってるはずだ。ぜひ最後まで読んでみてくれ。
はじめに:発注者支援業務の働き方は「楽」なのか?

発注者支援業務って、施工管理よりは働きやすいってよく聞くんですけど、実際のところどうなんでしょうか?

働きやすさという点では、たしかに施工管理よりも余裕がありますね。私が施工管理をしていたのは20年以上前ですが、当時は休みも少なく、書類仕事も夜遅くまでかかっていました。それに比べて発注者支援業務では、休日の確保や残業の少なさ、そして仕事の責任の重さという面でも、精神的な負担は軽くなったと感じています。
施工管理と発注者支援業務、どちらがきつい?
施工管理の仕事は、現場の段取りや下請けとの調整、材料発注といった多岐にわたる業務をこなしながら、現場が終わってから書類仕事に追われるなど、心身ともにハードな環境でした。
特に20年前は週休二日制度も浸透しておらず、工期内に終わらせるために休みなしで動く現場も珍しくありませんでした。現在は改善されつつありますが、それでも業務量と責任の重さを考えれば、やはり施工管理のほうが「きつい」と言えるでしょう。
一方、発注者支援業務では、たとえば段取りや数量のミスがあっても直接的な損失にはなりません。もちろん、発注者の信頼を損なうようなミスは許されませんが、施工管理に比べて気持ちに余裕を持って取り組めるのは確かです。
転職後に感じた「働き方の違い」
発注者支援業務の一日は、まず発注者職員とのスケジュール確認から始まります。その後は現場の立会や巡回、書類の作成といった業務がメインになります。
施工管理時代のように、ひとつの現場に集中するのではなく、複数の現場を平行して見るため、タイミングによっては忙しくなることもあります。
ただ、段取りに追われたり、突発的なトラブル対応に振り回されるというよりは、比較的落ち着いて業務を進められる環境です。時間的な余裕があるぶん、ミスを防ぎながら丁寧に仕事ができるようになりました。
現場の緊張感とは違った責任の重さはありますが、心身のバランスを保ちながら働けるという点では、大きなメリットだと感じています。
発注者支援業務の働き方の実態

施工管理と違って、発注者支援業務ではどんな働き方になるんでしょうか?実際の現場での動き方や、発注者との関係性についても教えてもらえますか?

発注者支援業務は、現場の管理というより調整役の側面が強いですね。発注者と受注者、関係機関の間をうまく取り持つことが求められますし、相手によって柔軟な対応が必要になる場面も多いです。忙しさは業務や配属先によって大きく変わりますが、全体としては施工管理時代より余裕を感じました。
現場管理ではなく「調整役」になる働き方
発注者支援業務では、発注者の立場で現場全体を見渡し、必要に応じて受注者と調整を行います。職員の多くは複数案件を抱えており、すべての現場に足を運ぶのは難しいため、技術者がその“目”となり、状況を把握して報告する役割を担います。
ただし注意が必要なのは、あくまで私たちは業務委託として発注機関に派遣されているという点です。発注者側に立つとはいえ、公務員ではなく民間企業の人間です。
その認識が曖昧だと、受注者に対して高圧的な態度をとってしまったり、本来の権限を超えた行動をしてしまう恐れがあります。中立的な立場を意識し、受注者・発注者双方との信頼関係を築く姿勢が重要です。
発注者(国交省・自治体)とのやりとりがメイン業務
発注者支援業務は、基本的に発注者職員の指示のもとで動きます。国交省や都道府県など、発注機関によって職員のスキルや経験値も様々です。
ときには、入省して間もない若手職員から指示を受ける場面もありますし、現場経験の豊富なベテラン職員と組むこともあります。相手の特性に応じて、柔軟にコミュニケーションを取っていくことが求められます。
発注者支援業務は単なる「指示待ち」では務まりません。相手が何を求めているのかを先読みし、自主的に動く姿勢が評価される現場です。
定時退社は本当に可能?残業の実態
「発注者支援業務は残業が少ない」とよく言われますが、実際にはケースバイケースです。
たとえば、災害復旧業務など、スピードが求められる現場では残業や休日出勤が発生することもあります。夜間工事への対応が必要なケースもありますし、工種によって忙しさは異なります。道路工事は関係機関との調整が多く、比較的残業が発生しやすい傾向にあります。
また、発注機関によっても業務量は変わります。国交省は全体的に業務が多く、残業が発生しやすい一方で、県レベルの案件では書類量も少なく、現場への立会も限定的なため、定時での帰宅がしやすい傾向です。
私の経験上、国交省の監督補助(特に道路関連業務)以外であれば、ほとんどの現場で定時退社が可能でした。
発注者支援業務のデメリット

発注者支援業務って、働きやすいとは聞きますけど、逆に「ここはしんどい」と感じる部分もあるんじゃないですか?具体的に教えていただけますか?

そうですね、確かに働きやすさはありますが、仕事の裁量が限られていたり、現場との距離感に違和感を覚えることもあります。それに、国や自治体のルールに従って動くぶん、柔軟性に欠けると感じる瞬間もあります。
意思決定権がない仕事のストレス
発注者支援業務では、基本的に現場や書類に関する最終判断を下す立場にはありません。あくまで「確認し、発注者に報告する」という役割に徹する必要があります。
そのため、自分の判断でスムーズに物事を進めたいというタイプの方にとっては、もどかしさを感じることがあるでしょう。
もちろん、判断を委ねることで精神的な負担が軽減されるという側面もありますが、「自分で決められない」ことにストレスを感じる方には向かない業務かもしれません。
現場に出ないことで感じる物足りなさ
施工管理では、現場に立ってモノを動かし、完成に向けて直接関わる充実感がありますが、発注者支援業務ではその感覚は希薄になります。
仕事の中心はデスクワークであり、現場に出るのは状況確認や立会のときがほとんど。構造物を「自分がつくった」という実感は得にくいです。
ただし、巡回や進捗報告などを通じて、現場を陰から支えているという責任感とやりがいを感じる方も多くいます。
国や自治体のルールに縛られる働き方の窮屈さ
発注者支援業務は、基本的に国や自治体の規定に則って進められます。庁舎内で発注者と同じ空間で働くため、自由に残業をすることも難しいケースがあります。
発注者が定時で帰るならこちらも帰らざるを得ない。逆に、発注者が残業していれば付き合わざるを得ない。そういった「空気を読む働き方」が求められることもあります。
さらに、公務員と同じような目で見られるため、私生活でも行動に注意が必要です。飲酒トラブルや交通違反などは、会社の信用に関わる重大な問題として扱われかねません。
こうした環境にストレスを感じる人にとっては、窮屈な職場だと感じるかもしれません。
発注者支援業務の課題と今後の展望

発注者支援業務って、最近どんどん需要が増えている印象がありますけど、現場レベルではどんな課題があるんでしょうか?今後の展望もあわせて教えていただけますか?

そうですね。業務自体は拡大傾向にある一方で、人手不足や成長機会の少なさといった課題も感じています。キャリアパスや業務内容の幅にも限界がありますから、今後どう改善していくかがポイントになりそうです。
慢性的な人手不足と業務負担の増大
発注者支援業務はある程度の現場経験が求められるため、即戦力となる人材の確保が難しいのが実情です。
施工管理や設計などの業務を経験した中堅〜ベテラン技術者がターゲットになりますが、建設業界全体が人手不足であるため、発注者支援業務も同様に慢性的な人材難に陥っています。
その結果、少人数で複数の案件を抱えるケースも珍しくなく、特に若手の育成が追いついていないことが課題となっています。
技術者としての成長機会の限界
ICTの活用や新工法への対応が進む中で、発注者支援業務に従事する技術者も最新の知識やスキルを求められます。
ティーネットジャパンでは、研修や外部講習の機会は用意されていますが、あくまで基本的な内容が中心で、自主的に深堀りして学ぶ姿勢がなければ、技術者としての成長は頭打ちになります。
また、業務の性質上、同じ種類の仕事を繰り返す傾向があるため、スキルの幅が広がりにくいという問題もあります。
民間施工管理と比べたときのキャリアの選択肢
民間の施工管理職では、現場代理人から所長、支店長といった形で段階的にキャリアを積むことができますが、発注者支援業務ではその道が限られます。
基本的には「担当技術者」または「管理技術者」としての2択で、管理技術者になるには経験年数や上司の推薦、試験など複数の条件を満たす必要があります。
つまり、一定以上のキャリア形成が難しく、長期的に見て行き詰まりを感じる方もいるかもしれません。
将来的にどう成長したいか、どのような働き方を続けていきたいかを明確にしておくことが重要です。
施工管理から発注者支援業務に転職する前に考えるべきこと

施工管理から発注者支援業務に転職したいと考えている方も多いと思いますが、事前に確認しておくべきポイントって何でしょうか?向き・不向きについても教えてもらえますか?

はい。発注者支援業務はたしかに働きやすい面もありますが、「楽そうだから」という理由だけで転職すると後悔することもあります。自分の適性や職場との相性をきちんと考えることが大切ですね。
どんな人が発注者支援業務に向いているのか?
発注者支援業務は、ある程度現場経験を積んだ土木技術者であることが前提です。さらに、パソコンを使った書類作成が中心になるため、内勤が苦にならない人に向いています。
また、発注者や受注者、地元住民や関係機関など、さまざまな関係者とのやりとりが多いため、コミュニケーション力の高い人、調整ごとが得意な人が活躍しやすいでしょう。
転職前に確認すべき「働き方のリアル」
「体力的に楽そう」「公務員っぽい働き方ができそう」という理由で発注者支援業務に興味を持つ方もいますが、業務には細かな注意力や倫理観が求められます。
また、発注者支援業務におけるミスは、信用問題や工事全体の遅延に繋がる可能性があるため、単純な作業と思っていると痛い目を見ることになります。
「楽だから」という理由で転職して後悔しないために
この仕事は、ワークライフバランスを改善できる可能性がある一方で、個人の資質が強く問われる業務です。求められるのは、技術力・経験・倫理観・対人スキルの4つ。
ティーネットジャパンのような会社であっても、個人の力量が業務の質に直結するため、誰にでも務まる仕事ではありません。
施工管理よりも気が楽になる部分はあるかもしれませんが、責任の所在や評価基準は明確です。だからこそ、「楽そうだから」ではなく「自分に合った働き方かどうか」という視点で慎重に判断してほしいと思います。
まとめ:発注者支援業務は本当に自分に合っているか?

いろいろと聞かせてもらいましたが、結局のところ発注者支援業務って自分に合っているかどうかが大事ですよね。最後に、これまでの話を踏まえて、判断材料になるようなポイントを教えてください。

おっしゃるとおりで、「発注者支援業務に向いているかどうか」を見極めることが一番大切です。施工管理と比べて楽かどうかではなく、自分の適性とキャリアに合っているかを考えてみてください。
施工管理と発注者支援業務、それぞれのメリット・デメリットを整理
施工管理の魅力は、構造物を自分の裁量で動かしていける達成感、職人たちと一丸になって現場を進める一体感にあります。残業代や手当もあるため、収入面でも有利な側面があります。
一方で、精神的・肉体的な負担が大きく、休みも取りにくいなどの課題も抱えています。
発注者支援業務は、残業が少なくカレンダー通りに休みを取りやすい、デスクワーク中心なので定年後も続けやすいという特長があります。ですが、構造物を作る実感が得にくい、転勤の可能性がある、キャリアの選択肢が狭いというデメリットもあります。
「楽な仕事」ではなく「適性のある仕事」を選ぶ重要性
発注者支援業務は、ある程度の実務経験と、冷静な判断力、対人スキルが求められる仕事です。ワークライフバランスを重視する方には魅力的ですが、「楽そうだから」で選ぶとミスマッチになりやすい職種でもあります。
この業務は今後も、維持管理やインフラ整備においてニーズが高まっていくと予想されています。だからこそ、企業選びや発注機関の特性、業務内容の違いまで含めて、自分に合った環境を探す姿勢が大切になります。
最後にひとつだけ。たとえ一度は合わないと感じても、それは「この仕事に向いていない」という意味ではありません。自分にとってベストな条件や働き方を見つけるまでは、経験を積みながら調整していくことも、立派なキャリアの築き方だと思います。